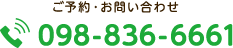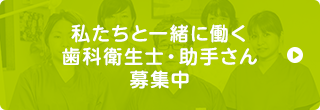二段階麻酔法|痛みを回避する手法とは

こんにちは、ユキデンタルオフィスの小場です😀
「注射」というワードが出てきただけで、拒否反応を示す患者さんは実に多くいらっしゃいます。
私自身も歯科医師になる前は麻酔されることがとても苦手だったので、麻酔に対してご不安な気持ちを持つ心情は十分に理解しているつもりです。
しかし、残念なことに歯科治療で痛みを抑えるために麻酔をすることは避けて通れません。
だからこそ、当院はできる限り麻酔の痛みを回避できる心配りを大切にしています。
前回のブログ「歯科恐怖症には、2つの「ない」を目指す」でもすこし触れましたが、今回は、具体的な麻酔の痛みをすくなくする方法をご説明します。
なぜ痛みを抑えられる?二段階麻酔法とは
痛みを回避する麻酔方法としては麻酔針の痛みを和らげるため、2回に分けて患部を痺れさせていく「二段階麻酔法」を採用しています。
そもそも、なぜあんなにも麻酔の針は痛いのか?というと麻酔針を刺す際の「チクッ」とした痛みが原因です。
したがって、注射の針を刺す前の行程から痛みを感じにくくするように、針を刺す部位に対して、あらかじめ「表面麻酔」と呼ばれる処置を施してから麻酔をおこなうのです。
表面麻酔とは歯ぐきに塗るタイプのお薬のことで、あらかじめ患部に表面麻酔を塗布して、数分~10分程度じっくりと浸透させることで、歯ぐきの知覚を麻痺させるのです。
もちろん、表面麻酔に関してはまったく痛みを感じませんのでご安心くださいね😀
痛みをおさえるためにはテクニックも大切
ほかにも痛みを回避する工夫がありますが、皆さんは何であると想像しますか?よく効く麻酔を使うことでしょうか?それとも、最新の器具を使うこと?
これら器具や薬剤も、もちろん大切ですが1番肝心なことは「丁寧に麻酔を打つこと」です。
痛くない麻酔のテクニックとしては「麻酔針を打つ場所・薬剤を注入するタイミング・一定速度で麻酔を打つ」これら3つの工夫を取り入れて、針を刺すときの痛みをできる限り減らしていきます。
具体的には術者(歯科医師)の指先の圧力がかからないように、針を患部に「置く」ようにして刺していきます。
ほかにも、一気にどっと注射液が入ってしまうと圧力は高まり、痛みが増してしまうので「そーっと」麻酔液を注入する技量も必要です。
個人差はありますが、患者さんのなかには「何かが触れたような感覚だけで、麻酔の痛みは感じなかった」とおっしゃっていただけたケースもすくなくありません。
歯科恐怖症には、2つの「ない」を目指す

こんにちは。ユキデンタルオフィスの小場です😀
当院では「痛くない・恐くない」この2つの「ない」歯科医院を目指しています。
「歯科医院が怖い」「治療は痛いから嫌だ」といった気持ちは、多くの人が抱いている、ごく当たり前の感情です。
歯の治療が怖いことは、たとえ大人であっても決して恥ずかしいことではありません。
実は私自身も歯科医師になる前は歯医者が怖くて「痛くない歯科医院があればいいのに」と、よく思ったものです。
だからこそ、患者さんの気持ちは大いに理解・共感できます。
そんな私だからこそ、歯科恐怖症の方を含めて一人ひとりと向き合い、快適な医療が提供できるように3つの具体的な取り組みをおこなっています。
歯科恐怖症対策➀ 徹底した事前のヒアリング
歯科医院に対して特にトラウマが強い方などは、歯科医師を目の前にすると緊張してしまい、言いたいことが言えないという方も多いです。
このような理由から、当院では問診票の段階で恐怖心を感じる方に、あらかじめ申告ができるようにしています。
その問診票をもとに、恐怖心の強い方には麻酔を伴わない治療から始めてみるなど、個々の治療方針を立てていきます。
また持病のある方などはお薬手帳を持参してもらい、万一当院で処方する薬と飲み合わせる薬の相性が良くない場合は、主治医と連絡を取り合って慎重な判断をおこなうケースもあります。
歯科恐怖症対策② 患者さんのご意向が第一
来院される患者さんのなかでは、セカンドオピニオンの方もいらっしゃいます。
なぜセカンドオピニオンしたのか、理由はさまざまですが、その根底のなかには「自分の気持ちを聞かれずに、流れ作業的に治療された」という気持ちを持って来院される方がすくなくありせん。
当院では治療のご予算や見た目のご希望などはもちろんですが、治療に対する不安や歯科医院に対する不信感のお気持ちまですべて受け止めますので、どうぞご遠慮なくお話しください。
歯科恐怖症対策③ できる限り痛みがないような配慮
誰でも痛いのは嫌ですし、嫌な思いをすれば敬遠したくなるのは当然でしょう。
当院では、物理的な痛みを解消してリラックスした状態で治療に臨めるように「二段階麻酔法」と「笑気吸入鎮静法」を導入しています。
あまり聞き慣れない専門用語ですが、どのような治療法なのか?
詳しくは、次回以降のブログで解説いたしますね。
ただの口内炎だと侮ってはいけない理由

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀
なかなか治らない口内炎に困った人は多いでしょう。
私は、もともと琉球大学医学部附属病院の歯科口腔外科に勤務していた経歴もあり、親知らずの抜歯を希望される方はもちろん、なかには「長引いている口内炎」が気になって来院される方がすくなくありません。
「口内炎など、我慢すれば勝手に治るものだ」と思っている方もすくなくありませんが、私が長年の臨床経験からぜひ皆さんにお伝えしたいことがあります。
それは「ただの口内炎だと思って侮るなかれ」ということです。
口内炎は「2週間」がキーポイント
結論から言うと、2週間以上長引いている口内炎や1cm以上の大きな口内炎は注意が必要な場合があります。
なぜ注意が必要なのかと言うと、口内炎(口腔粘膜疾患)の背景には、非常に多くの病変が潜んでいる可能性があるからです。
口腔粘膜疾患は、大まかに言うと3つのパターンに分類できます。
①あくまでお口のなかに限られた病変で、投薬や生活習慣の改善などで治癒する
②全身疾患の部分的な症状として口腔粘膜に症状をあらわすケース
例)手足口病・ヘルパンギーナ・ベーチェット病など
③悪性腫瘍のケース
来院される患者さんのなかでもっとも多いケースは➀ですが、②のケースもすくなくありません。
そして上記のなかで、もっとも用心するべきは③の悪性腫瘍の場合であり、これが「口内炎を甘く見てはいけないよ」というメッセージにつながります。
定期検診では粘膜部分まで細かく診てもらうことが大切
お口のがん発生頻度は、がん全体の1〜3%程度と決して多くありませんから、一般の方にはあまり認知されていないのが口腔がんの現状です。
しかし、他のがんと違うところは「患部を直接見られる」ことです。
つまり口腔がんは比較的、早期発見しやすいがんと言えます。
お口のなかは食べ物や入れ歯などで刺激に晒されて汚れやすい部分なので、容易に感染を起こしやすいです。
また、本来の典型的な形で病変が現れず、むしろさまざまな変化を起こした状態であらわれる場合が数多くあるのが口内炎の特徴と言えます。
このような特殊性からユキデンタルオフィスでは、通常の歯科検診から粘膜部分までていねいに検査して、良性・悪性の見極めをおこなうことで、わずかな変化を見逃しません。
万一、なにか疑われるようであれば、すぐに専門機関へ紹介できるパイプの太さも当院の強みです。
むし歯治療のトラウマをなくすために心がけていること

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀
むし歯治療をおこなう際に「キュイーン」という、あの耳ざわりな音・・・。
子どもはもちろんのこと、大人の方であっても決して気持ちのよい音ではありませんよね。
想像しただけで恐怖心がよみがえってくる方も、なかにはいらっしゃるのではないでしょうか。
患者さんが歯医者で感じる「恐怖心」の根底には2つの原因があると思っています。
1つ目は「肉体的な痛みからくるもの」
2つ目は「精神的な理由によるもの」です。
ユキデンタルオフィスでは、恐怖心の根元の問題である痛みやトラウマを取り除いて、歯医者へ向かう足取りをすこしでも軽くしたいと常に考えています。
幼少期の歯科トラウマは生涯に渡って記憶に残るもの
むし歯治療で特に注意を払わねばいけないのは小さな子どもさんです。
なぜならば、子どものときの「歯医者さんで痛いことをされた!」「無理やりおさえつけられた」といった記憶は、生涯に渡って根深く残るからーー
そう確信したのは、長年の臨床経験によるものです。
大人の患者さんのなかでは、重度のむし歯を長期間に渡って放置しており「もう抜歯するしか為す術がない」と思えるほどになってから来院される方もなかにはいらっしゃいます。
そのなかで「子どものころに歯医者でひどく痛い思いをしたから、ずっと歯医者を懸念していた」という幼少期の苦い経験を打ち明けてくれる方はすくなくありません。
しかし、こういった方がわざわざ重い腰を上げて当院に来てくれたのに、すでにむし歯の進行が進みきっているので、効率的な治療を施すのが困難になるのです。
典型的な悪循環ですよね・・・。
「もっと早く来てくれれば、痛みも治療期間もすくなくなるのに・・・。」
歯科医師として、いつも悲しい気持ちになります。
そういった背景から、私は「小さな子どものときから歯医者へのマイナスイメージを与えてはいけないのだ」と痛感しているのです。
子どもの治療に対する当歯科医院の考え
ユキデンタルオフィスでは、子どもさんのやる気を引き出して「治療としっかり向き合える環境作り」を重視しています。
(大人でもそうですが)だいたいの子どもさんの場合は、1回ですべてのむし歯治療は終えられないと思っていただいた方がよいです。
要するに何回か通院が必要となるので、初歩的な段階から恐怖心を与えてしまっては、治療のゴール(むし歯完治)が遠のいてしまいます。
お子さんの治療は「決して焦らず、ゆっくり段階を踏んで治療を進めていくこと」が肝になってきます。急がば回れ、なのです。
例を挙げると
・初診時はむし歯に使う器械に慣れてもらうだけで終わらせる
・初期段階の簡単なむし歯の治療からはじめて「思っていたよりも痛くない」「これなら我慢できる」を実感してもらう
・麻酔を使用した上級者向け治療はあえて後からおこなう
こういった工夫で徐々に、お子さんの自信と信頼関係を育てていきます。
ユキデンタルオフィスでは妊婦さんからご高齢の方、すべての世代に安心して通っていただける取り組みに今後も努めて参ります。
むし歯が発生するしくみとリスク
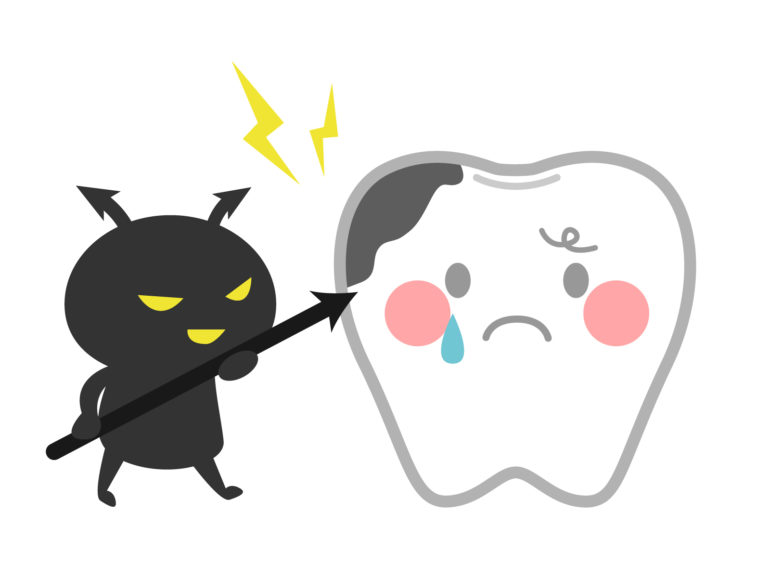
こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀
今回は「そもそもどうやってむし歯になってしまうの?」といった原因論についてと、むし歯治療をおこなった「そのあとのリスク」に関してもお答えしていきます。
むし歯になるしくみとは
むし歯が発生してしまう第一の原因は「むし歯菌(ミュータンス菌)が出す酸」によるものです。
ミュータンス菌は、食物に含まれる糖質をエサにして酸という糞のようなもの(代謝物)を出して、その酸によって歯が溶かされて穴が開いてしまう状態を作り出します。
歯は酸性環境に対して非常に弱いので、むし歯菌によってお口のなかが酸性状態になり続けると、歯が溶けてくるというわけです。
そのほかにも、むし歯は「環境的素因」と「遺伝的素因」の2つが大きく影響していると考えられていますので、むし歯を予防していくためには、この2つが重要なキーワードとなってきます。
・環境的要因……むし歯菌が滞在している時間や糖質の多い飲食物を召し上がる
・遺伝的要因……生まれ持った歯の質やだ液量、歯並びなど
などが挙げられます。
歯周病菌とむし歯菌の違い
ちなみに、以前のブログ「歯周病が発生するしくみとリスク」でも歯周病のしくみについてお伝えしたのですが、歯周病菌とむし歯菌に関して大きく違うところが1つあります。
皆さん、分かりますか?
それは、むし歯菌は「細菌そのもの」が悪さを起こして歯が溶けてしまうのに対して、歯周病菌は、細菌から逃れるために歯が防御反応を起こした結果「自らが」顎の骨を溶かしてしまう、という点。
歯や顎の骨に対して悪さを働くという点においては一緒なのですが、根本的な作用はまったく違うのです。
少々、難しいクイズでしたね😅
むし歯を治したあとのリスクとは
むし歯の部分を削ったあとの歯はプラスチックや金属の詰め物、神経を取った歯に対してはかぶせ物を装着します。
しかし、治療すればずっとむし歯にならず安心だ、というわけではないのです。
「なぜ治療した歯がむし歯になってしまうのだ」といった声が聞こえてきそうですが、残念ながら、これは人工物の宿命です。
歯とかぶせ物の間には月日を追うごとに微細な「すき間」があらわれ、すき間から二次的なむし歯になることがあります。
また、詰め物の材質によっては天然歯よりもプラーク(汚れ)がつきやすく、神経を取った歯は痛みこそ感じないものの、栄養源の補給ができない状態にあるので非常にもろく、歯が割れるリスクが高まってしまうのです。
ユキデンタルオフィスでは、むし歯を治したあとのリスクについてもしっかりと説明し、患者さんに最適なかぶせ物や詰め物の提供に努めています。
歯石除去は自分でできるのか?

こんにちは。ユキデンタルオフィス・院長の小場です😀
ときどき、患者さんから「歯石除去を自分でやっている」と言われることがあります。
患者さんとしては「歯の汚れを取るだけで、わざわざ歯医者にかかりたくないから自分でやってしまいたい」といったお気持ちなのでしょう。
しかし、本当に歯石は自分で取れるのでしょうか?
結論から言いますと、自分で歯石を取る行為は、メリット以上にリスクが多過ぎるので決しておすすめはできません!
部分的な歯石除去だったら自分でもできる?
通販サイトを確認すると、実際に私たちが現場で使用しているものに近い手用スケーラー(手で歯石を取る器具)が販売されていましたので、医療従事者でなくとも手に入りやすい世の中になってしまっているのが現状です。
こうなれば、患者さん側としても「自分でも歯石は取れるのでは?」と思ってしまっても無理はないでしょう。
たしかに、下の前歯など鏡で確認しやすい箇所であれば、手先の器用な方でしたら自身でもおこなえるでしょう。
しかし、あくまで「ごく一部の歯石除去」しかできません。
歯石は自身で確認ができない箇所にこそ、たくさん付着している可能性があるのです。
自分で歯石除去をおこなったときのリスク➀
歯石は、とくに付着しやすい箇所があります。
それは「下の前歯の裏側」と「上の奥歯のほっぺた側」。
なぜ上記の場所にたまりやすいのかというと、歯石は歯垢がだ液の成分と固まり石のような硬さの「歯石」になるので、だ液が多く分泌されているところに、よりたまりやすいから。
ほかにもブラッシングのときに出血した歯は歯周病の可能性があり、歯石が付着しているケースが十分に考えられます。
要はどの場所であっても歯石は付着するので、鏡で見えるところだけ歯石除去をしても、残念なことにあまり意味はないのです。
ちなみに、歯科医師である私自身でも(下の前歯の歯石を取るのならまだしも)上の奥歯の歯石を取ることは到底不可能です。
自分で歯石除去をおこなったときのリスク②
自身で歯石除去をおこなったときの、もう一つの大きなリスク。
それは「中途半端に歯石を取ると、さらに歯石がたまる環境を作り出す恐れがある」ということ。
「せっかく歯石を取ったのに、またすぐに歯石がつく」とは、一体どういうこと?と感じた方もおられるでしょう。
実は、歯石や歯周病菌はデコボコしている面により付着しやすい性質を持っているのです。
自分で歯石を取れたとしても、完璧に取り切ることはまず難しいでしょうから、かえって歯の凹凸を作り出してしまい、さらに歯周病菌が付着しやすい悪循環を自ら生み出してしまう場合があります。
歯石を取ったあとは、どうしても歯面が粗造になります。
ユキデンタルオフィスの予防処置では、歯石を取ったあとは専用の研磨剤を使用して、ていねいに磨き上げ歯の表面を滑らかな状態にして、歯石の再付着を予防します。
歯周病菌は人から人へうつるのか

「私のお口のなかにある歯周病菌は、子どもに感染するのでしょうか」――まだ小さなお子さんがいる保護者の方からこういった質問をよく受けます。
結論を言いますと、歯周病菌は細菌の一種ですので、世間を賑わせている新型コロナウイルス菌と同様に人から人へ感染します。
生まれたての赤ちゃんに歯周病菌はいない
歯周病菌やむし歯菌は、親子間や夫婦間など家族関係から感染する場合が多いです。
つまりリスクファクターは「日常的に濃厚接触をせざるを得ない方」となり得ます。
考えてみると、生まれたての赤ちゃんに歯周病菌やむし歯菌はいませんよね。
歯周病菌やむし菌は、だ液のなかに潜んでいるので、たとえば「キスをする」「近い距離で話しかける」「食器を共用する」などといった行為や習慣から感染すると考えられています。
何歳ごろに歯周病菌をうつされるのか
では、歯周病菌は一体いつ頃のタイミングでうつされているのでしょうか。
小学生くらい?それとも成人してから?
実はさらに前の段階、なんと「よちよち歩き」のころから歯周病菌やむし歯菌をうつされている可能性があります。
(「感染の窓」といって、1歳7カ月前後に感染のピークを迎える時期と言われています。)
また、1歳を過ぎたころと言えば、多くのお子さんが離乳食の時期が終わる時期でもあり、幼児食へ移行する時期です。
このころには食べられるメニューも増えていますし、保護者のなかには大人と同じお菓子・味付けで食べさせている方もいらっしゃるようです。
こういったさまざまな生活背景があり、結果的にお子さんがむし歯になってしまうわけですね。
「うつされる」と「感染する」は違う
このような話を聞くと「スキンシップは控えるべきなのか」と思われるかもしれません。
しかし、小さなお子さんへのスキンシップは親子間の愛着関係と非常に深い結びつきがありますので「木を見て森を見ず」の状態になりかねません。
わかっていただきたいのが、歯周病菌がお口のなかに入ってきたとしても、歯周病菌単体であれば悪さを起こさないということ。
歯周病が爆発的に増殖すること(=感染)が問題なのです。
つまり、歯周病菌がお口に入ってきたとしても、それ自体を恐れる必要はなく、増殖できる環境でなければ歯周病は発症しません。
>>「家庭でできる歯周病予防とは」
お子さんのいるご家庭へ向けたアドバイスとしては「食器の共有などは止めた方がベターですが、スキンシップ自体は減らさないでも大丈夫」とお伝えしたうえで「家族すべての方にむし歯菌・歯周病菌を減らす努力を心がけていただくことも忘れないように」と、付け加えています。
歯周病菌を減らす具体的な対策は
・3カ月ごとのメンテナンスを受けて歯のクリーニングを受けていただく
「予防歯科(むし歯・歯周病・粘膜疾患の予防)」
・正しい歯磨き方法で毎日ブラッシングする
・キシリトール配合のガムなどを毎日召し上がっていただく
これらの心がけで歯周病菌・むし歯菌を減らす対策をしていれば、さほど神経質にならなくても心配はいりません😀
当院の歯周病治療費・回数の目安
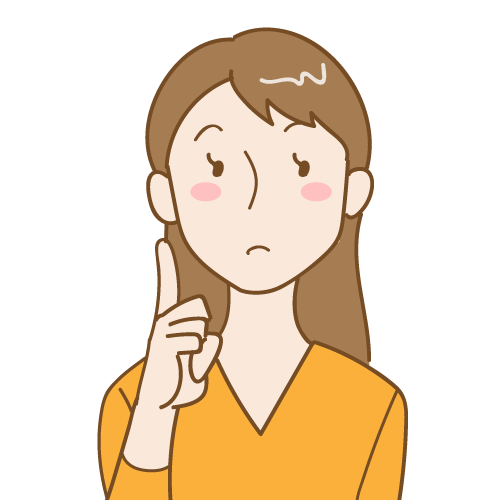
「今日の治療費は一体いくらだろう……」「先生に歯周病の治療が必要だと言われたけど、歯周病の治療っていくらかかるの?」など言ったように、治療費に関しては頭を悩まされますよね。
保険診療の歯科治療費の目安
また「今日こそは治療費について聞きたい!」と心の内では思っていても、いざ歯医者へ到着すると痛みへの恐怖心や緊張感などが相まって、結局は聞くタイミングを逃す方も少なくないようです。
歯周病治療の90%以上は保険適用
ユキデンタルオフィスの歯周病にまつわる治療費用に関しては、基本的に健康保険が使えますのでさほど高額な費用は請求しません。
しかし、例外的に健康保険の適用外(自費治療)となるケースもあります。
それは重度の歯周病で抜歯の必要性が出たケースに、自費治療となる義歯・インプラントを選ばれた場合。
もちろん、健康保険が使える入れ歯やブリッジの被せ物も患者さんご自身で決めていただけますので、費用面を気にされる方はどうぞご安心なさってくださいね。
歯周病の治療費用と回数
➀初期歯周病のケース
通院回数は4回(週1回通院なら1カ月)程度が目安で、費用は総額で約8000円ほどです。
初期の歯周病治療では、歯石除去を中心に炎症を起こした歯ぐきの改善をおこないながら、セルフケアのスキルアップをはかります。
初期治療が終わったあとは3カ月ほど経過を観察し、再び退院していただきます。
その際に歯ぐきの炎症がすっかり治まっていれば、定期検診にうつりますし「まだ炎症が引いていないな~」となれば、さらに1カ月ほど治療に専念してもらいます。
②中期歯周病のケース
通院回数は4~8回程度が目安で、費用は総額で総額で13000円〜17000円ほどかかってきますが、歯ぐきの炎症状態などによって回数や費用に個人差があります。
治療内容は基本的に初期の歯周病と同じ内容です。
「なんでこんなに回数がかかるの?」と、ときどき質問を受けることがありますが、
・一気に歯石を取ると強い知覚過敏や急激な歯肉退縮を引き起こすリスクがある
・機械的清掃で手早く歯石を取ることもあれば、深いポケットにこびりついた歯石は手作業で地道に取ることもある。
要するに長い時間をかけて沈着をした歯石除去にはそれなりの時間がかかる。
などの理由があるからです。
③重度歯周病のケース
結論を言うと、重度歯周病の通院回数や費用の予測を立てるのは非常に困難です。
また、外科手術(フラップ手術)の有無でも異なります。
フラップ手術とは、歯肉を切開することで病巣となっている歯石や感染している組織を取り除く方法です。
重度になると歯周病を完治するのは厳しいので、中期くらいに病状を落ち着かせるのが狙いです。
1年間で6~12回程度の通院をしてもらうと、年間で15000円前後の費用がかかってきますので、治療費の総額は通院回数×年数分がかかるイメージです。
そこにフラップ手術をおこなう場合のみ、追加で2000円程度かかってきます。
歯周病かも?と感じたらチェックしたい「歯周病3つの進行段階」

「歯磨きをするたびに、歯ぐきから出血がある」
「歯がグラグラしていて、物が噛みにくい」
「起床時の口臭が気になる」
これらの症状があれば、歯科医師としてまず疑うのは歯周病ですが、もちろんむし歯や外傷、または全身疾患が付随して起こりうる歯の病気もあります。
しかし、2014年(平成26年)に厚生労働省がおこなった「患者調査の概況」によれば、むし歯の総患者数(=継続的に治療を受けていると推定される人のこと)は、むし歯では約185万人、歯周病に関しては約332万人とのデータがあります😅
むし歯と歯周病の患者数、両者の間にはおおよそ2倍の差があるのですから、私が最初に疑うべき疾患は歯周病、といっても差し支えないでしょう。
今回は、そんなごくありふれた歯の病気・歯周病とはどのようにして進行していくのか?という知識を得ていただき、デンタルIQを高めましょう。
歯周病進行のステージは3段階ある
以前のブログ「歯周病が発生するしくみとリスク」でも軽く触れましたが、歯周病の進行ステージは大まかに初期・中期・重度の3つに分類できます。
➀初期の歯周病
・歯周ポケット(歯と歯の間のすき間)は3~5mmあり、わずかながら顎の骨が溶け始めている
・歯ブラシをしたときに出血がある
・歯ぐきが赤く、すこしの腫れぼったさがある
・この段階では自覚症状がない患者さんがほとんどで、目に見える大きな変化はない
②中期の歯周病
・歯周ポケットは4~7mm程度あり、顎の骨が本格的に溶けだす
・初期に比べて出血や腫れが強くなる
・歯周病菌由来の口臭を感じる人もいる
・体が不調なとき、歯が浮いた感じや腫れが強くなることがある
・歯の動揺や口臭などの症状から自覚症状を感じはじめる人が出る
③重度の歯周病
・歯周ポケットは8mm以上となり、顎の骨が半分以上無くなった状態で歯が大きく揺れる
・歯ぐきから膿が出て、痛みを感じる場合がある
・食べ物がうまく噛めなくなったり、硬い食べ物を食べると歯が痛んだりすることも
なんとなく、を確かな歯科知識に変えよう
「前々から歯周病かなと思っていたのだけれど、足が重くてなかなか来られなかったんです。」こうおっしゃる患者さんは、決して少なくありません。
言わずもがな、そういった方たちが重度の歯周病になっているケースが後を絶ちません。
逆を言えば、軽い歯肉炎程度の状態でも「歯周病かもしれないので、すぐに診てほしい!」と真剣な表情で来院される患者さんもおられます。
両者の違いはなんだろう?――私なりに考えた結論は、知識の差です。
歯周病の自覚が「なんとなく」ありながらも、実際に自分が歯周病かというのは、知識に乏しいと不確かなままですし、どのような治療をされるかも見当がつかず「なんとなく」来院を控えてしまうのだろうと推測しています。
地道ながらもブログの情報発信を通して「なんとなく」を「確かな知識」に変えていき、早期発見・治療につながることを私は期待しています😀
家庭でできる歯周病予防とは

歯周病のおもな原因はプラーク(=歯垢)であり、プラークコントロールが歯周病予防の「肝」です。
家庭でおこなえる歯周病予防・対策としては、やはり「最低でも1日に1回、5分間はブラッシングすること」これに尽きます。
よく、「歯磨き粉の薬用成分で歯周病が治る」と勘違いされている患者さんがいますが、歯磨き粉はあくまで補助的な道具に過ぎません。
例えるならば、キッチンにたまったヌメリやカビを落とすには、ただ洗剤を吹きかけるだけで汚れは落ちませんよね。
やはり、ブラシやスポンジですみずみまで磨かないとキレイにはなりません。
歯にたまった垢(プラーク)も同様にお考えいただければ、分かりやすいでしょう😀
効果的なブラッシング方法のポイント
➀歯ブラシの持ち方と選び方
・ヘッド部分が奥歯まできちんと届くものを選択しましょう。
無難なのは「コンパクトヘッド」と記載されている歯ブラシを選ばれると、小回りがききやすいです。
・毛のかたさは歯ぐきを傷つけにくい「ふつう」か「やわらかめ」を選択。
・毛の材質は、ナイロン製よりしなやかで耐久性も優れており、水はけもよく衛生的な飽和ポリエステル樹脂がおすすめです。
・補助的な歯間清掃用具(歯間ブラシやフロスなど)を積極的に取り入れましょう。
歯ブラシだけで落とせる歯の汚れは6割程度ですが、フロスなどを活用すれば、8~9割まで歯の汚れが落とせるとされています。
②歯磨きをするタイミング
効果的な時間帯は、夜寝る前です。
なぜかと言うと、就寝時はだ液の分泌が減ることで、お口の細菌が非常に増殖しやすいから。
寝る前に丁寧に歯磨きをおこなうことで、あらかじめお口の細菌を減らしておけば、ばい菌たちの活動を封じ込められるというわけです。
「忙しくて1日に何回も磨ける余裕はない」という方は、夜寝る前だけでもていねいに磨くことを心がけましょう。
③歯の磨き方
・歯ブラシの毛先を歯に対して垂直にあてがい、歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間を意識して、細やかな微振動でブラッシングする「スクラビング法」が歯周病予防に効果的。
・歯を磨く強さは、桃を磨くようなやさしい圧でおこなう。
効率的な歯磨きを習得できるよう、私たちが取り組んでいること
ここまでお伝えしましたが、「じゃあ、私に合った補助的清掃用具ってなんだろう?」といったさまざまな疑問や不安が沸いてくる方もいらっしゃるでしょう。
お口に合わせた歯ブラシをご提案したり、効率的な歯磨き法を指導したりするために、ユキデンタルオフィスでは患者さんが普段お使いの歯ブラシを持参していただき歯磨き指導をおこなっています。
実際に使用している歯ブラシを使ってアドバイスすることで「自宅に帰ったあとでも歯科医院で教わったことをスムーズに実行しやすい」と考えているからです。